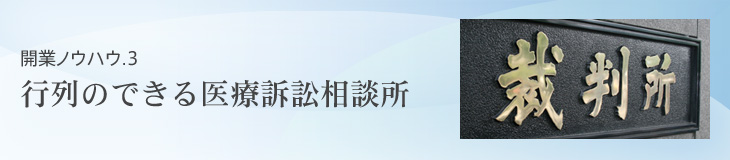

森山経営法律事務所
弁護士 森山満
刑事医療過誤の基礎知識
医療過誤は、まず刑事責任と民事責任とを分けて考える必要があります。
刑事で扱うのはあくまでも個人の行為なので、行為を行った担当医が業務上過失致死罪、業務上過失致傷罪として処罰の対象となります。ただしチーム医療では、処分が病院の医科長にまで及ぶケースもあります(いわゆるさいたま医大総合医療センター抗癌剤過剰投与事件における最高裁平成17年11月15日判決)。
平成11年の都立広尾病院の点滴事故において関係者が刑事責任を問われて以来、医療過誤における刑事責任の追及が増加傾向にあります(これは同事件で病院長らが医師法21条の警察への届出義務違反で刑事責任を問われたため、警察への届出件数がそれまでと比較して急増したことも関係しています)。
医療過誤において、刑事責任が問われるパターンとして、まず、誤薬(薬剤の種類、量、投与方法等の単純な間違い)、患者の取違え、異型輸血、医療機器の操作ミスなどの人為的エラーの場合があります。これらはいわゆるうっかりミスであるために、ミスによって患者を死亡させたり重大な傷害を与えた場合は、まず刑事責任を免れません。
人為的エラーのうちでも、患者の転倒転落パターン(たとえば看護師が患者を介助しているときに不注意で転倒させてしまった場合など)は、患者自身の行為が介在しているので刑事責任には結びつきにくいのですが、自ら行動できない新生児や意識不明の患者などを転落させたり転倒させたりすれば刑事責任を問われることになるでしょう。
以上に対して、医師の診療行為の過程で発生した医療過誤は、医療水準(医師としての専門家水準)が問題となるため、刑事責任の追及は本来は謙抑的であるべきです(しかし、福島県の大野病院事件に代表されるように、近時、診療行為の場面でも積極的に刑事責任が問われるケースが増加しています)。
診療行為に関しては、術中・術後の管理の甘さによって患者を死亡させたような場合は、特に厳しく刑事責任が問われる傾向にあります。
胆のう摘出術での刑事判例
5歳の胆のう炎の患者に対して内視鏡による胆のう摘出術を実施した際、執刀医がトロッカーで下大静脈を損傷しため開腹に切り換えところ、胆のう剥離の過程で癒着が激しかったために総胆管を結紮・損傷してしまいました。
その結果胆汁が腹腔内にもれ、胆汁性腹膜炎を合併したため1週間後に大学附属病院に転医させましたが、この患者は転医してから43日後に死亡しました。
このケースの場合、検察官から手術を担当した担当医師2名に対して、捜査終了後にいきなり公判請求(正式起訴)がなされました。
●東京地裁判決(平成16年5月14日) 両医師とも禁固1年、執行猶予3年
この事件では、検察官から
開腹に切り換えた後に胆のう摘出を継続した過失、
総胆管を損傷した手技上の過失、
損傷に気づきにくい手術器具を使用した過失、
術中に胆道造影を実施し総胆管損傷の有無を確認すべき義務を怠った過失、
術後に胆汁混じりの腹水がドレーンから継続して排出しているのを確認した時点で総胆管損傷を疑いERCPなどの検査を行うべき過失
が主張されましたが、裁判所は(1)~(3)の過失を認めず、(4)(術中管理)と(5)(術後管理)の各過失を認めて有罪としました。
このように、手術適応や手技ミスそのものでは裁判所は容易に刑事上の過失を認めることはありませんが、術中・術後管理のミスで患者が死亡した場合には厳しい態度を採るのが一般です。
この種の事案で、検察官が起訴に積極的になり、また裁判所も有罪の心証に傾くのは、この程度の手術で(すなわち胆のう炎の手術で)本来は患者は死亡するはずがないのに死亡させたという点を重視しているように思われます。
つまり、刑法上の考え方として、(1)当罰性(処罰の必要性)及び(2)可罰性(処罰を正当化する根拠/罪刑法定主義がその典型)という二つの考え方があるところ、本来患者が死亡するはずのない手術で死亡した場合などは当罰性ありとして、少々過失の程度が軽くても(可罰性の観点からは業務上過失致死罪としての過失は人の生命に直接危険を及ぼすほどの重大な過失に限られるはずですが)積極的に処罰すべきだ、と考えるわけです。
この観点から、上記事件でたとえば最初の内視鏡の段階でトロッカーで下大静脈を損傷し、その結果、患者が出血多量で死亡したと仮定した場合は、今度は下大静脈損傷の手技ミス自体が捉えられて処罰される可能性が高いことになります。
なお、筆者の経験では、地域によって検察・警察の医療過誤への対応はさまざまであり、起訴に積極的かどうかで地域差があるように思われます。
また、産科の事故で担当医が事故から一年以上も経って突然逮捕された福島県立大野病院のケースでは、医学会を中心に各方面から猛反発が起きたために、最近では従前に比べて若干刑事責任の追及が緩やかになってきているようにも思われます。
とはいえ、刑事責任の追及が全体として厳しくなっている傾向に変わりはなく、また、最近では以前とは違って医療過誤の刑事事件で無罪となったケースがほとんどないために、いったん検察官から刑事責任ありとして立件されると責任を争うことは困難です。
最近では、検察官による起訴は略式起訴といわれる罰金刑が多くなっていますが、これは被疑者である担当医ら側が正式裁判(公判)での裁判を受ける権利を放棄する同意書に署名捺印する代わりに罰金刑で済ませてもらうものです。
しかし、略式起訴による罰金刑であっても有罪であることには変わりはありませんので、いったん起訴され有罪となってしまうと、今度は厚生労働省(医道審議会)による行政処分(罰金刑以上の刑事処分を受けたケースはほとんどすべてが業務停止3か月以上)を免れないのが現状です。
民事医療過誤の基礎知識
医療過誤のうち、担当医らの刑事責任が問題とならない場合でも、次に民事上の損害賠償責任が問題となります。この場合でも「過失」の存在が必要ですが、民事上の過失は刑事上の過失(業務上過失致死傷罪としての過失)よりも軽い過失でもかまわないため、医療事故がいったん民事訴訟に発展すると、裁判所は患者救済の観点から医療現場が予想している以上に医療機関側に厳しく過失を認定する傾向にある点は注意が必要です。
医師の診療行為は大きく分けて診断行為と治療行為とに分けられます。
診断行為の場面では、患者の主訴なり所見、実施した検査結果などから、特定の悪性疾患や、患者の状態の悪化(急変など)などの悪しき結果を担当医が疑うことができたか(これを「予見可能性」といいます)が争いの中心となります。
次に、治療行為の場面では、上記の意味での予見可能性があることを前提として、治療法の選択に誤りはなかったか、手術中などでの手技ミスや術中・術後管理上のミスなどが問題となります。ここでは、他の治療法を採るべきではなかったかとか、術中の手技操作で別の操作をすべきでなかったかといった「回避義務」の有無が争いの中心となります。
最後に、診断行為でも治療行為でもそれ自体ミスがなかったとしても、手術の危険性について説明が甘かったことなどを理由に「説明義務」違反を問われる可能性があります。
(民事医療過誤の類型)
診療行為
診断行為
誤診類型予見可能性の有無が中心問題治療行為予見可能性の存在を前提として回避義務の有無が中心問題
治療法の選択ミス(手術適応の有無など)
手技ミス(但し、予想外の損傷などでは予見可能性が争いとなる場合もある)
術中・術後管理のミス
説明義務違反・・・手術など侵襲的行為への有効な同意を得るための説明、
複数の選択肢からの選択のための説明、治療方針・治療結果等の説明など
なお、常勤の勤務医やアルバイト医師の医療過誤における民事上の責任主体は、当の本人のほか、本人と雇用契約(委託契約)を結んでいる医療機関の開設者 (経営主体)です。
開設者は、患者と診療契約を結んでいて、診療にあたる医師らは診療契約を履行するうえでのいわゆる「履行補助者」として位置づけられるため、開設者は患者との関係で、診療契約違反を理由に損害賠償責任を免れることはできません。
したがって、患者側から損害賠償の相手方として訴えられるのは、通常は開設者なのです(患者側としてもその方が賠償金を取りやすいという面があります)。また、担当医ら個人も医療過誤を起こした本人として患者に対する直接の加害者的地位に立つため、民法の不法行為を理由として責任を負います。最近は、患者側の担当医らに対する感情的なしこりが強いのか、開設者のみならず、担当医ら個人も開設者と一緒に被告として訴えられるケースが増えてきているように思われます。
判決で過失が認定され、損害賠償責任が確定された場合は。原則として判決で認められた賠償金や弁護士費用などの訴訟費用は、医療損害賠償保険から填補を受けることができます。
ただし、次に述べるように医療機関側にとって民事訴訟の提起を受けることは、信用ダメージのほか、百害あって一利もありませんので、トラブルに巻き込まれた場合は可能な限り、医師賠償責任保険からの保険金支出を得て訴訟前の示談で終わらせるのが得策といえます。
(民事医療過誤訴訟の現状)
現在、医療過誤訴訟の一審での和解率(判決に至らないで訴訟の途中で和解で終わる率)は5割程度です。また、判決で終了する一審事件のうち、患者側の勝訴率は35%~40%です。和解で終わる事件では、そのほとんどが医療機関側が過失(責任)のあることを認めて和解金を支払って終了していると考えられますので、医療過誤訴訟全体のうち一審で医療機関側が金銭を支払う形で終了する事件は、判決及び和解で終了する事件とを併せて全体の7割程度に達している計算となります。
しかも、医療機関側が一審で判決で勝訴したとしても、患者側から控訴されると今度は高裁で逆転して負ける可能性がないとはいえません。一般の民事事件では、そのほとんどが高裁の第二審で一審の地裁判決がひっくり返る可能性はないのですが、医療過誤事件では、かなりの割合で医療機関側勝訴の一審判決がひっくり返る可能性があります。統計はありませんが、筆者の経験では恐らく最低でも2~3割程度が高裁段階でひっくり返っていると思われ(一審で医療機関側が勝訴したのに、高裁段階で和解で終了するケースをも含めると恐らく5割以上に達しているのではないかと思われます)、最近はますますその割合が高くなっているのではないかと考えられます。
以上からいえることは、医療機関側として患者側から訴えられても、結局は責任が認められる形で金銭を支払って終了することになるため、訴訟を受けて立つことは労力を費やし信用ダメージをこうむるだけで何の得にもならないということです。
そこで、最近では訴訟前の段階で、示談で終了するケースが増えてきているように思われます。全国における一審における訴訟件数は平成16年の1110件をピークとして、平成17年の999件、平成18年の912件と、漸減傾向にあります。
これは、医療過誤トラブルが決して減ってはいない現状を前提とする限り、訴訟前の示談の増加が大きな理由ではないかと考えています。
臨床医にとって「医療水準」とはなにか
医療過誤訴訟における過失の認定は、それが予見可能性の有無であれ、回避義務の有無であれ、「医療水準」という言葉がキーワードとなります。
医療水準とは医師としての専門家水準を意味します。裁判所は従前から医療水準とは学問としての医療水準ではなく、「臨床医学の実践としての医療水準」として考えてきました。
しかし、具体的にどのような場合に医療水準以上の診療行為といえるのか、何が医療水準以下の診療行為なのかとなると今ひとつはっきりしませんでした。たとえば、診断を誤った場合に、10人の医師のうち1人や2人は診断を誤ると考えられるのなら過失はないといえるのか、あるいは新しい治療法の実施が問題となっている場合に、学会などで当該治療法についてのガイドラインがあるかないかで結論が異なるのかといった具合です。
この医療水準に関して、新規の治療法の実施が問題となったケースとして有名な判決が平成7年6月9日の最高裁判決です。
事案は昭和49年当時、未熟児網膜症の光凝固法という治療法の実施義務(そのための転医義務)が争われたケースです。当時、その地域のある病院ではすでに光凝固法による治療を始めていました。
そこで、未熟児網膜症を診断した医師が、光凝固法による治療を受けさせるため患者をその病院に転医させなかったことについて、保護者がその医師の病院を訴えたのです。
ところが、光凝固法についての治療法のガイドライン(厚生省(当時)の研究班による治療指針)が医学雑誌で公表されたのはこの事件の直後の昭和50年8月のことでした。そこで、この事件での高裁は、そのことを重視して、このケースの昭和49年当時は光凝固法が未だ有効な治療法として確立していなかったことを理由に、医師が転医を怠ったことは過失ではないと判断しました(その結果、患者側である控訴人らの請求を棄却しました)。患者側は最高裁に上告しました。
最高裁判決(平成7年6月9日) 高裁の判決を破棄差戻し
上記の控訴審判決までは、裁判所は概ね「平均的医師」がその治療法を採るか否かを問題として、学会を始めとして公の治療ガイドライン(指針)等があればその治療法は医療水準にあるが、なければ医療水準に達していないという思考法を採る傾向にあったといえます。
しかし、この平成7年最高裁判決はこれに対して異議を唱えたものでした。
この判決の中で最高裁は、医療水準について「知見」について問題とすべきこと、知見の「相当程度の普及」は、「当該医療機関の性格」を考慮すべこと明らかにしています。
ここに「知見」とは、その時点で「専門的研究者の間で有効性・安全性が是認された情報」をいいます。診断基準ないしは治療基準が確立された情報にかぎらず、多少の異論があってもかまわないとされています。
ここで大切なのは、たとえばある新しい治療法の選択が問題となっているケースで、当該医療機関が勉強不足でその治療法に関する知見を有していなくても責任を問われるということです(「知らなかった」ではすまされないということです)。
そのうえで、前記最高裁判決は、「……知見の普及は、医学雑誌への論文の登載、学会や研究会での発表、一般のマスコミによる報道等によってなされ、また、当該疾病を専門分野とする医師に伝達され、次第に関連分野を専門とする医師に伝達されるものであって、その伝達に要する時間は比較的短い」と判示しています。
このことから、新規の治療法などで未だガイドライン等で指針が示されていなくても、論文や研究発表などによって当然医学的知見として備えることが期待される場合には、たとえ開業医であってもその医学的知見を備えておくべきことが期待される場合は、その医学的知見はその開業医にとっての医療水準となるということです。
また、診断行為における「誤診」が争いになるようなケースで(誤診類型)、「平均的医師」なら誤診もやむを得ないと考えられる事案であっても(たとえば10人の医師のうち、1人や2人は誤診がありえる場合でも)、次に述べる事例のように裁判所が医師に対して医学的知見の具備を厳格に要求する結果、裁判上は過失責任が認められる結果となってしまいます。
心筋梗塞の見落し
夜間、31歳の男性患者が上腹部痛、腹部膨満感、全身の倦怠感などを訴えて救急車で病院に運び込まれました。
この患者は精神疾患や肝障害の既往があったので、担当医はまず肝臓疾患を疑い入院措置をとったものの血液検査もせず心電図もとらなかったところ、患者は翌朝心筋梗塞で死亡してしまいました。
一審は、心筋梗塞の典型的な症状がなかったため、心筋梗塞と疑わなかったことはやむを得ないとして請求を棄却したのですが、遺族は控訴しました。
大阪高裁判決(平成2年4月27日判決) 約5200万円を支払え
この高裁判決は、実は医療水準についての見解を述べた前記平成7年最高裁判決よりも以前の判決です。
このケースでは、担当医の判断が結果的に誤診であったわけですが、高裁は「……診断を誤った場合は、一般的医療水準から考えて右誤診に至ることが当然であるようなときを除き、債務の履行が不完全であったというこができる」と述べて、本件では患者の症状は心筋梗塞に典型的なものではなかったにせよ、その存在を窺わせるような症状が存在していたのであるから、当該誤診がやむを得なかったものとは認められないと判断しました。
この判決ではさらに「心筋梗塞は、急性で死亡率の高い疾患なのであるから、その可能性が比較的小さくても優先的にその該当の有無を検討しなければならない」とも述べています。
以上から言えることは、誤診類型では、医療現場の感覚で「結果的に誤診であって過失はない」と思われるケースであっても、裁判所は(特に重大な疾患の場合は)誤診が当然である場合を除き(極端にいえば10人の医師がいれば10人とも誤診するような場合を除き)、過失を認めるということです。
したがって、医療機関側としては「医療水準に照らして、10人の医師が10人とも誤診するはずである」旨を事実上立証しなければならないことになります。
しかしながら、このケースで争いになった医療水準上の問題は、「患者の初期症状が心筋梗塞と矛盾していたか否か」という点であるところ、心筋梗塞で典型的な症状が出ない症例はいくらでもあることを考えると、医療水準上担当医は初診時心筋梗塞を鑑別の対象とすべきであったということになってしまいますので、結局この訴訟で医療機関側は最初から勝ち目がなかったといえましょう(本件で医療機関側は初診時の心音聴取でラ音が聴取されなかったことや、心筋梗塞が40歳未満では稀であることなどを主張しましたが、裁判所はいずれも本件での心筋梗塞の発症を否定する理由にはなりえないとしています)。
かぜと診断したら急性喉頭蓋炎で、重度の脳性まひに
ある政令指定都市で、公設の夜間専用の救急医療センター(当番制で開業医が詰める診療所)に、10歳の子供が発熱、息苦しい、吐く、たんが出ることなどを訴えて来院しました。
担当医は急性咽頭気管支炎(かぜ)と診察して、「のどが少し赤いけれど大丈夫だよ」と子供に声をかけネブライザーの施行と抗生剤を処方して帰宅させたのですが、実はこの子供は急性喉頭蓋炎で、帰宅してから窒息状態となり心肺停止状態になりました。
すぐ救急車を呼んで病院に運び込んだのですが重度の脳性まひになり、家族が損害賠償請求訴訟を起こしました。
横浜地裁判決(平成17年9月29日) 一時金約1億円、付添介護費用28万円~56万円/月を死亡時まで支払え
この事例も前記の心筋梗塞の見落しと同様、誤診類型に属するものです。
急性喉頭蓋炎は、わが国では小児には稀な疾患とされ、この事例の担当医も15年の経験の中で一度も経験したことがなかったためか、頭から急性喉頭蓋炎を疑っていなかったようです。しかし、判決では、急性喉頭蓋炎が嚥下障害などの進行してからの特徴的な症状は初診時には現れていなかったものの、初期症状としては矛盾しないので、急性喉頭蓋炎の可能性を考えなかったこと、子供を帰宅させてしまったことには過失があるとしています。
医療水準の問題としては、急性喉頭蓋炎の臨床経過の理解のほか、どれほど確率が小さい疾患であっても小児科医として常に念頭に置いておかなければならない疾患といえましょう。
本件担当医は不幸にして「落とし穴」にはまってしまったわけですが、裁判所は重篤な疾患の誤診は基本的に許さない態度を採っている点は注意が必要です。
開業医の医療水準
開業医は検査設備も限られていることが一般ですので、もともと正確な鑑別診断を行うこと自体が困難といえます。
したがって、誤診類型で開業医に期待されている医療水準は、疾患の正確な診断ではなく、専門病院や総合病院に転医させるべきか否かを見極める点にあるといえます。
ある開業医のところに頭痛・発熱等の通院中の男児が深夜大量の嘔吐をし、その後も治まらなかったため、翌朝開業医の診察を受けところ、開業医は急性胃腸炎・脱水症等を疑い、700ccの点滴を施して帰宅させました。しかしさらに嘔吐が続くので同日再度来院した患児に対し、医師はもう一度700ccの点滴を施して帰宅させました。
しかし帰宅後も嘔吐が続き、早朝になって意識が混濁した状態で市立病院に入院しましたが、最終的に原因不明の急性脳症により重度の脳性まひになってしまいました。
本人及び家族が損害賠償請求訴訟を起こしたところ、高等裁判所は、意識障害の兆候があったと断定できないので、一般開業医の医療水準上、急性脳症の発症を疑って高次の医療機関に転送をする義務があったと認めることはできないとして、原告の請求を棄却しました。そこで家族は最高裁判所に上告しました。
最高裁判決(平成15年11月11日) 破棄差戻し
最高裁は、本件で意識障害の兆候の有無が問題なのではなく、2回目の診察の時点で1回目の点滴投与等の治療によっても症状が改善せず、かつ2回目の治療の最中にも症状の改善が見られなかったのであるから、担当医はその時点で病名を特定できないまでも当該医院では適切に対処できない何らかの重大な緊急性のある病気にかかっている可能性が高いことを認識(予見)できたはずだと判断しています。
この点から、開業医は、「自分では手に負えないな」と思った時点で他の高次の医療機関に転医させる義務が生じ、それをしないで手遅れとなった場合は、特定の疾患を診断できなかったことがやむを得なかったとしても責任を問われることになりましょう。
まさに開業医は、地域のかかりつけ医として軽い疾患の治療にあたる一方、他方では重大な疾患の場合はより高次の医療機関に転医させる役割が求められるわけです。しかし、裁判所の考え方は、重大な疾患の場合の転医の遅れを基本的に許さず、結果的であれ手遅れであれば開業医の責任を基本的に認める傾向にある点で、開業医にとっても裁判所の判断は厳しい状況にあるわけです。
このような裁判所の態度が、最近における開業医の「怪しい患者」はなんでもかんでも高次の医療機関に送ってしまえばよいという風潮を招いているように思えてなりません。
診断的治療の半年間に、肺がんが転移して手遅れに
10年以上も前のケースです。ある30代前半の男性が健康診断で10ミリ程度の異常陰影(腫瘤陰影)が見つかり、公立のがん専門病院を訪れました。
担当医は結核種と肺癌の両方を疑い、血液検査、腫瘍マーカー、気管支鏡での細胞診を行いましたが、白黒つきませんでした。
ツベルクリン反応が強陽性だったので、抗結核剤を投与しながら陰影が増大するかしないかを確認する目的で毎月のように胸部レントゲンでの経過観察を行いました(現在のようにCTガイド下胸腔鏡による生検等は一般的ではありませんでしたので、当時は確定診断するために残された方法は開胸肺生検しかなく、診断のために経時的に陰影の増大傾向を追跡するやり方が主流でした)。
しかし腫瘤陰影は半年たっても大きくならず、半年後の再度のCT写真でも初診時と比較して変化がみられなかったため、担当医は半年後の再受診を指示しました。
ところが、半年後に患者が受診したときは、肺癌がすでに縦隔リンパ節に大きく転移してしまっており、すでに手術は不可能の状態でした。患者は約2年後に死亡し、遺族が病院開設者と担当医を訴えました。
名古屋高裁判決(平成15年11月5日判決) 慰謝料合計3600万円を支払え
このケースで担当医は半年後の再受診を指示した時点で完全に肺癌の疑いを捨てていたわけではありません。その点では予見可能性はあったわけです。
したがって、診断行為が問題となったケースですが、担当医に予見可能性があることは前提として、その先のさらなる確定診断のための検査の実施義務が問題となったケースです。
具体的には、主として肺癌の確定診断のための開胸肺生検の実施義務(回避義務)の有無が問題となりました。
医療機関側は、当時の医療水準として、肺癌の診断プロセスとして、一定期間(一年程度)陰影の増大傾向を追跡して経過観察することは許されるし、また本件での開胸肺生検は左肺上葉を切除する結果となり肺癌の手術そのものと変わらないほど侵襲が大きいことから、この時点での現実的な選択肢とはなりえないなどと反論しましたが、裁判所は、本件で患者は肺癌であったことは間違いないのであるから、疑いが残っている以上は(予見可能性があった以上は)確定診断のための開胸肺生検をすべきであったと判断したわけです。
それでは、このケースで患者が開胸肺生検に同意しなかったらどうでしょうか。実際のケースでは担当医は患者に対して、開胸肺生検について説明したわけではありませんでしたが、患者が残る確定診断の方法として仮に開胸肺生検について担当医から説明を受けたうえで拒否した場合がここでの問題です。
まず、原則は担当医には開胸肺生検の実施義務があることが前提です。しかし、患者には自己決定権がありますから、かかる自己決定権の帰結として患者が当該開胸肺生検を拒否することは可能であり、その意に反してまで担当医は開胸肺生検を実施すべき義務を負うわけではありません。
しかし、ここで問題なのは、どれだけ担当医が開胸肺生検の必要性とリスク等について説明をしたかです。患者が開胸肺生検の意味をよく理解したうえで拒否するのなら問題はありませんが、ろくに理解しないまま同意しなかったのであれば適正な自己決定権の行使とはいえず、担当医は今度は説明義務違反の責任を負わされる可能性があります。
たとえば、本件で担当医が「開胸肺生検という方法もありますが、あなたも忙しいでしょうからしばらく様子をみることにしましょう」と言った程度で開胸肺生検の必要性やリスクについてきちんと説明せず、患者も忙しいから開胸肺生検に同意しなかったとした場合、患者の同意はありませんので担当医の開胸肺生検の実施義務はなくなると考えてよいわけですが、説明義務違反としての責任を問われる可能性がある点は注意が必要です。
医師の説明義務を理解する
患者には診療契約上に関して、自己決定権というものがあります。
まず、患者は特定の医療機関との間で診療契約を結ぶか否か、あるいは診療契約を継続するか解除するかという決定権があります。
次に、患者の診療契約上の権利として、たとえば内視鏡検査や手術など身体を傷つける侵襲的な医療行為に対して同意する権利があります(同意権)。医療機関側がこれを無視して勝手に手術などを行えば、原則としていわゆる専断的医療行為となり違法となります(場合によっては傷害罪として刑事責任を問われる可能性すらありえます)。
また、患者は診療契約上、今後どのような検査を受け、治療を受けるかといった診療方針についてすら自ら決めることができる権利があるとされています(選択権)。
患者の自己決定権といった場合、狭義には上記の診療契約上の権利としての同意権と選択権の二つを押さえておくことが大切です。
先の肺癌の事例は、医師に開胸肺生検義務があるとされたケースですので、患者にとって開胸肺生検を受けるか受けないかという選択肢はありません。しかし、開胸肺生検は侵襲が大きいため患者はこれに同意するかどうかという問題はなお残されているわけです。
では、医師の説明義務は上記の患者の自己決定権とどういう関係に立つのでしょうか。
患者が自己決定権を行使するためには、その前提として自己の病気が何であり、病状がどうであるか、今後の診療方針としてどのような選択肢があるか、それぞれの選択肢の内容、メリット・デメリットがなんであるか、仮に受ける予定の検査なり治療方法が身体に侵襲をもたらす場合、どの程度の侵襲(リスク)を受けることになるのかといった自己の診療に関する情報について正確に知らなければなりません。
この患者に対してその患者の診療に関する情報を提供しなければならないとされる医師の診療契約上の義務が説明義務といわれるものです。
したがって、説明不足で侵襲的な検査や治療について患者の同意を得たり、治療方針について患者に選択させたりした場合は患者の有効な同意や選択を得たことにはならず、医師は説明義務違反としての責任を問われることになります。
ここにいう「説明義務違反としての責任」とは、説明義務違反に伴う慰謝料にとどまるのが原則です。
たとえば、ある癌患者に対する治療方針として手術と抗癌剤療法の二つの選択肢があると仮定した場合、医師が抗癌剤療法についてろくに説明せず手術を実施したところ、患者は術中の合併症で死亡してしまったとします。患者は手術それ自体には承諾書を提出して承諾していたとするなら手術に対して同意は一応あったものと考えられます。
しかし、他に採りうる抗癌剤療法についての説明は受けていなかったのですから、抗癌剤療法という選択肢のあることや手術の危険性等について説明を受けていれば手術はやめにして抗癌剤療法を選択していたかも知れません。
実際には、患者は医師の勧める治療法を選択する傾向にありますから、このケースでは患者は医師から抗癌剤療法との比較における手術のメリット・デメリットの説明を受けていても手術を選択した可能性は高いわけですが、少なくとも「選択の機会を奪われた」という評価は可能です。
この選択の機会を奪われたという自己決定権(これは法律上は一種の人格権とされています)の侵害が説明義務違反による損害として捉えられ、慰謝料という形で損害賠償責任が認められることになるわけです。
では、この自己決定権侵害としての説明義務違反の慰謝料額はいくらくらいになるのでしょうか。
実は、この金額の決定は裁判所の裁量によります。過去の判例でも下は100万円程度から上は1600万円に至るまでさまざまです。
1600万円という慰謝料額を認めた判決(東京高裁平成11年5月31日判決)は、AVM(脳動静脈奇形)の患者に対して全摘手術を行った結果重篤な左片麻痺などの後遺障害が残ったというケースで、手術の適応は認めたものの、保存療法との比較における説明を怠った点で説明義務違反を認めたものでしたが、当時それまでの報告されていた当該手術の治療成績が非常に悪かったことから説明義務違反の程度が非常に重いと判断したことによります
夫の同意を得れば説明義務違反にはならない?
ある大学付属病院で出産時に起こったケースです。子宮筋腫があらかじめ判明していた妊婦に対して帝王切開による出産のため開腹を行ったところ、胎盤の癒着があり用手的に剥離したところ出血が止まりませんでした。
執刀医は出血を止めるには子宮筋腫がある子宮を摘出した方がよいと判断し、患者の夫に対して子宮摘出について説明しその同意を得ました。執刀医は子宮摘出に着手しましたが、子宮と右側卵巣との癒着が予想以上に癒着していたため、子宮とともに右側卵巣も摘出しました。
後日、妻本人から説明義務違反を理由に損害賠償請求訴訟を起こされました。
侵襲的な医療行為における同意権者はあくまでも患者自身であることから、夫の承諾(同意)では有効な同意を得たことにはなりません。
術中に予想外の事態が起きて緊急避難的に摘出するのであれば別ですが、このケースでは判決は子宮摘出の緊急性がない(いったん閉腹して再手術することも可能であった)と認定しています(なお、本件では患者本人は腰椎麻酔であったため医療機関側は夫が手術室内で患者本人の承諾を得ていたはずだと主張しましたが、判決では患者は児を娩出直後のことであって、かつ患者は酸素マスクをつけていたなどの事情から医療機関側の主張を認めていません)。
このようなケースでは、可能であれば術前に子宮を摘出しないで済みそうだと判断される場合であっても、万一のことを考え、可能であれば術前に「……のような事態が生じた場合は子宮を取ることもあります」と説明して同意を得ておくのがベターでしょう。
なお、この判決では子宮及び卵巣という女性にとって重要な臓器を摘出された点を捉えて、500万円という慰謝料額を認めています。
未破裂動脈瘤の予防的手術に失敗
未破裂動脈瘤の予防的手術をめぐる紛争は過去の裁判例でも比較的多いものです。
平成12年当時、言語障害、健忘等を主訴に69歳の男性が被告病院を受診したところ、検査の過程で左内頚動脈の狭窄とともに未破裂動脈瘤が偶然発見されました。
そこで、医師は開頭によるいわゆるコーティング術を勧め、これを実施したところ、患者は術後にてんかん重責発作を発症し遷延性意識障害となり、約1年半後に死亡しました。これに対して遺族が、損害賠償請求訴訟を起こしました。
大阪地裁判決(平成17年7月29日判決) 合計約3200万円を支払え
本件での未破裂脳動脈瘤に関する治療方針としては、まず(1)保存療法と(2)予防的手術の二つの選択肢があります。
また、予防的手術を選択するにしてもア)開頭手術、イ)カテーテルによるコイル塞栓術の二つの方法があり、さらにア)の開頭手術としては、i)クリッピング術とii)コーティング術とがありえます。
本件では、予防的手術のうち、イ)コイル塞栓術とア)i)のクリッピング術は適応がないとして、ア)ii)のコーティング術が採られました(判決では予防的手術を採用する場合の本件でのコーティング術の適応は特に否定されていません)。
さらに、本件では患者に動脈硬化による左内頚動脈狭窄症が認められていたために、脳梗塞の予防として(1)抗血小板剤を投与するという選択肢と、(2)特別な治療はしないで経過観察をするという選択肢が考えられました。
ただし、左内頚動脈凶作症に対して、(1)の選択をした場合は、未破裂脳動脈率の破裂率を高める可能性は否定できず、特に破裂した場合はより重症化するリスクが考えられました。
判決は、本件での未破裂脳動脈瘤の生涯破裂率と、未破裂脳動脈瘤に対して開頭手術を実施した場合の死亡・後遺障害罹患率(合併症率)が同程度であることを認定して(ともに約10%程度)、必ずしも予防的手術の実施が第一選択肢ではなかったことを前提として、本件で担当医が術前の説明で、
(1)本件未破裂脳動脈瘤の生涯破裂率について不正確な説明をしたこと(担当医は「3人か4人に1人、あるいは100人いれば20数人から30数人くらい破裂する」と説明)、
(2)左内頚動脈の狭窄に対して経過観察をする選択肢があることを説明していないこと、
(3)本件コーティング術の予防的効果はクリッピング術に比較して確実性が低いことを説明していなかった点で説明義務違反を認めました。
そして、判決では、患者が術前に開頭手術を嫌がっていたという事実を認定したうえで、担当医が上記説明義務を尽くしていれば患者は本件予防的手術を選択しなかった蓋然性が高いとして、死亡までの全損害についての損害賠償を認めました。
前述のとおり、説明義務違反としての効果は、患者の自己決定権侵害としての慰謝料にとどまるのが原則ですが、本件のように緊急性のない予防的手術等における失敗例では説明義務違反がなければ患者は当該手術を受けなかったであろうと認定され、結果までの全損害の賠償が認められる可能性がある点は注意が必要です。
侵襲的な医療行為に関する過失 4つのポイント
上記の未破裂脳動脈瘤の手術でもそうですが、それ以外のすべての侵襲的な検査や手術を行った結果、術中・術後にいわゆる合併症が生じて患者に悪しき結果 (死亡や後遺症など)が生じてしまった場合、患者側からは必ずといってよいほど、以下の4つの過失がセットで主張されます。
1.適応上の過失
そもそも当該検査なり手術を行う必要がないのに行ったという適応上の過失の主張。
2.手技ミス
手術適応があったとしても、術中に、手術手技にミスがあったから当該合併症が発生したという手技上の過失の主張。
3.術中・術後の管理ミス
仮に手技ミスがなくても、術中の管理を怠った、あるいは術後にちゃんとフォローすれば悪しき結果は防げたはずだ、との術中・術後管理上の過失の主張。
4 説明義務違反
最後に、以上の1~3の過失が否定されたとしても、術前に説明義務を怠ったとの主張。
実際、前記の未破裂脳動脈瘤のケースでは、原告である遺族側は(1)本件で予防的手術の適応がなかったこと、(2)説明義務違反、(3)てんかん重責発作を防止するための術中の管理上の過失を主張しました。
裁判所は、(1)(3)の過失を否定して(2)の説明義務違反だけを認めたわけですが、ここで大切なことは説明義務は医療機関側を守るためのものではなく、法律上はあくまでも医療機関側が責任を問われる根拠となるにすぎないという点です。
よく「あらかじめ危険性に関する説明を十分にしておけば多少の手技ミス等があっても許される」という現場の声を聞くことがありますが、そうではありません。裁判所の立場からすれば、手術適応や手技上の過失が否定せざるを得ない場合に最後に説明義務違反を根拠として医療機関側に対して賠償責任を問うことができないかを判断するのです。
この点で、医療機関側としては裁判上問題となった各過失や説明義務違反の全部の争点について排斥することができなければ裁判での全面的な勝訴は難しいことをよく認識しておくことが大切です。

